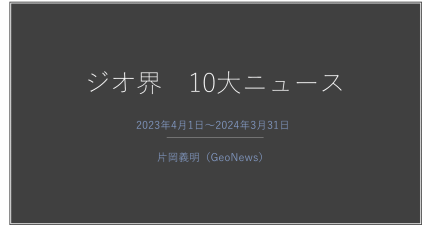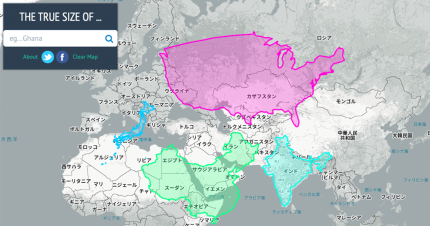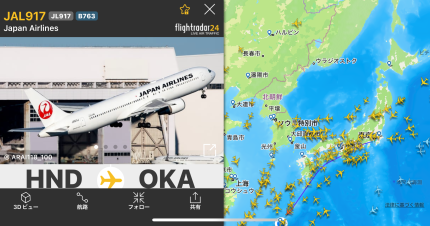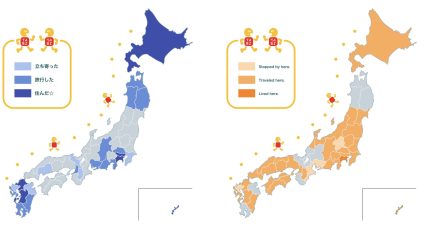【ジオ用語解説】スマートシティリファレンスアーキテクチャ
スマートシティの設計方法や実現方式を共有するためのリファレンス文書
近年、全国各地においてスマートシティ関連のさまざまな取り組みが行われていますが、産・官・学・民が地域課題解決や新たな価値の創出を目的として協働するためには多様なステークホルダーの間で設計思想や設計方法、実現方式などの“アーキテクチャ”を共有することが有効となります。このようなスマートシティにおけるアーキテクチャを、都市や地域がそれぞれ作成するのではなく、リファレンスとして参照できるようにしたものが、内閣府が公開している文書「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」です。
スマートシティリファレンスアーキテクチャは、第1版が2020年3月に公開され、現在は2025年3月に公開された第3版が提供されています。同文書はホワイトペーパーと導入ガイドブックが提供されているほか、2024年3月には補遺として「スマートシティ施策のロードマップ」、2024年9月には別冊として「スマートシティ~地理空間情報データ連携基盤」も公開されています。このほか、スマートシティの先行事例についてまとめた「スマートシティ・ガイドブック」や、スマートシティ関連施策に対する適切な評価の枠組みや評価指標を示した「スマートシティ施策のKPI設定指針」も公開されています。
これらの文書は内閣府のウェブサイトにダウンロードリンクが掲載されています。以下に、それぞれの概要を紹介します。
▽スマートシティリファレンスアーキテクチャ(ホワイトペーパー)
スマートシティリファレンスアーキテクチャの意義や戦略に加えて、自治体スマートシティ戦略の位置付けや検討ステップ、目指すべきビジョン、計画策定における考え方などについて、自治体による具体例なども織り交ぜながら解説しています。また、スマートシティの計画・実施・運営において遵守すべきルール(スマートシティルール)や、スマートシティ運営の担い手となる推進組織の位置付け、利用者に提供されるスマートシティサービス、収集したデータを補完して連携させるための「都市OS」の機能などについても紹介しています。このほか、都市OSを通じてデータ化・制御されるデバイスやネットワークなどのアセットや、都市OS以外の政府系・自治体システム、民間システム、都市OSが扱うデータの一覧なども掲載しています。
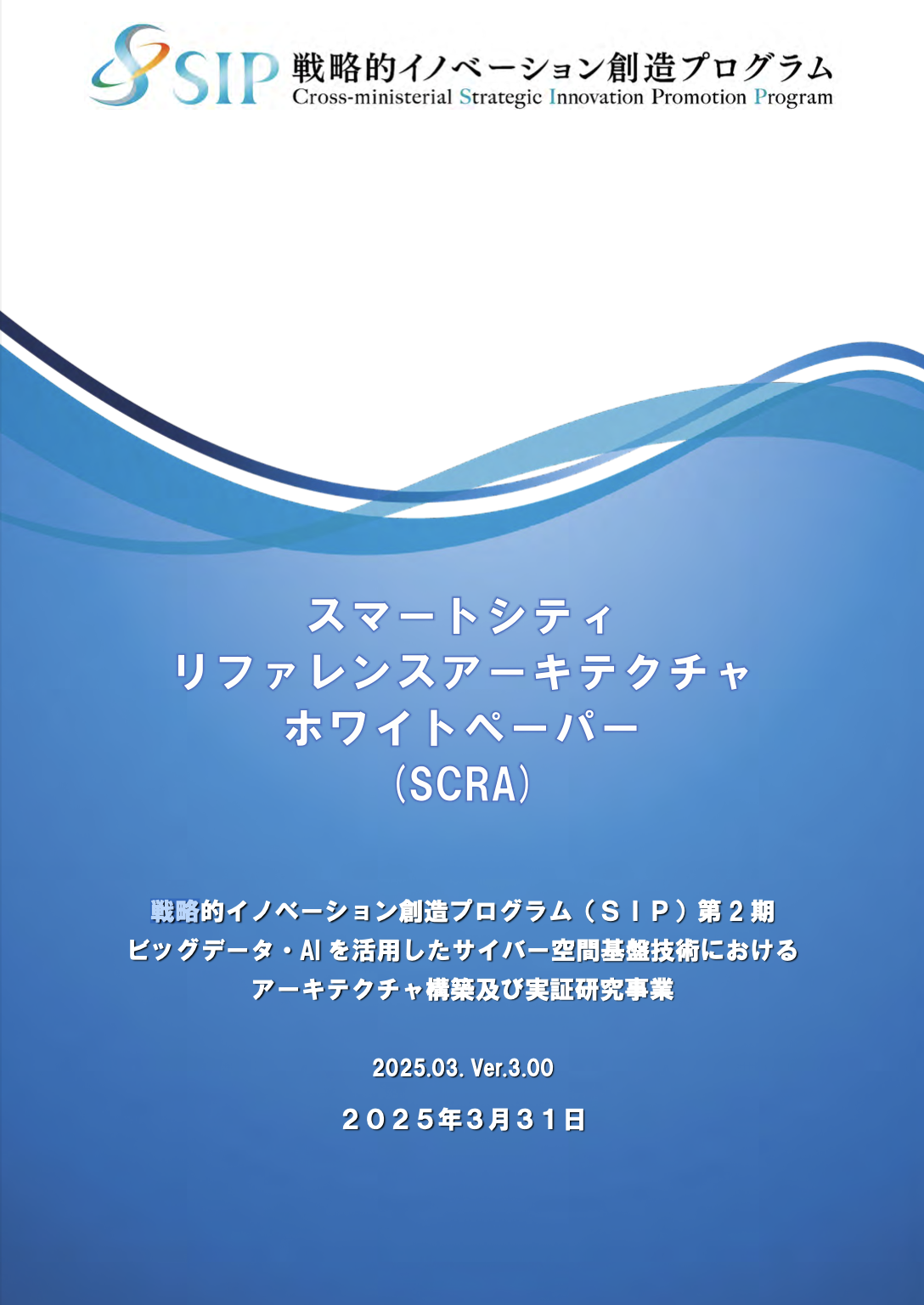
スマートシティリファレンスアーキテクチャ
▽スマートシティリファレンスアーキテクチャ(導入ガイドブック)
スマートシティリファレンスアーキテクチャのホワイトペーパーを理解し、活用しやすくするために図などを使って平易に解説した文書です。
スマートシティの実装に向けて必要とされる取り組み事項について、「都市経営」「データ連携」「横展開」の3つの観点で整理して段階的に行う施策や、その時々に実現するスマートシティの状況を示した文書です。期間を「2025年頃」「2030年頃」「2030年以降」に分けてまとめています。
都市OS上でさまざまな地理空間データの流通を促進するために、地理空間データ連携基盤に関する仕様を定義することを目的とした文書です。地理空間情報をデータ連携基盤として活用するために、既存の地理空間情報を「地図タイル」のデータとして整備、公開することにより、アプリケーション開発のコスト削減が可能となり、アプリケーションの横展開も容易になります。また、オープンソースの仕様を採用することでベンダーロックの防止にもなります。本書では地図タイルのフォーマットや地理空間データ連携基盤のシステム構成、機能やサービス、連携可能なデータなどについて解説しています。
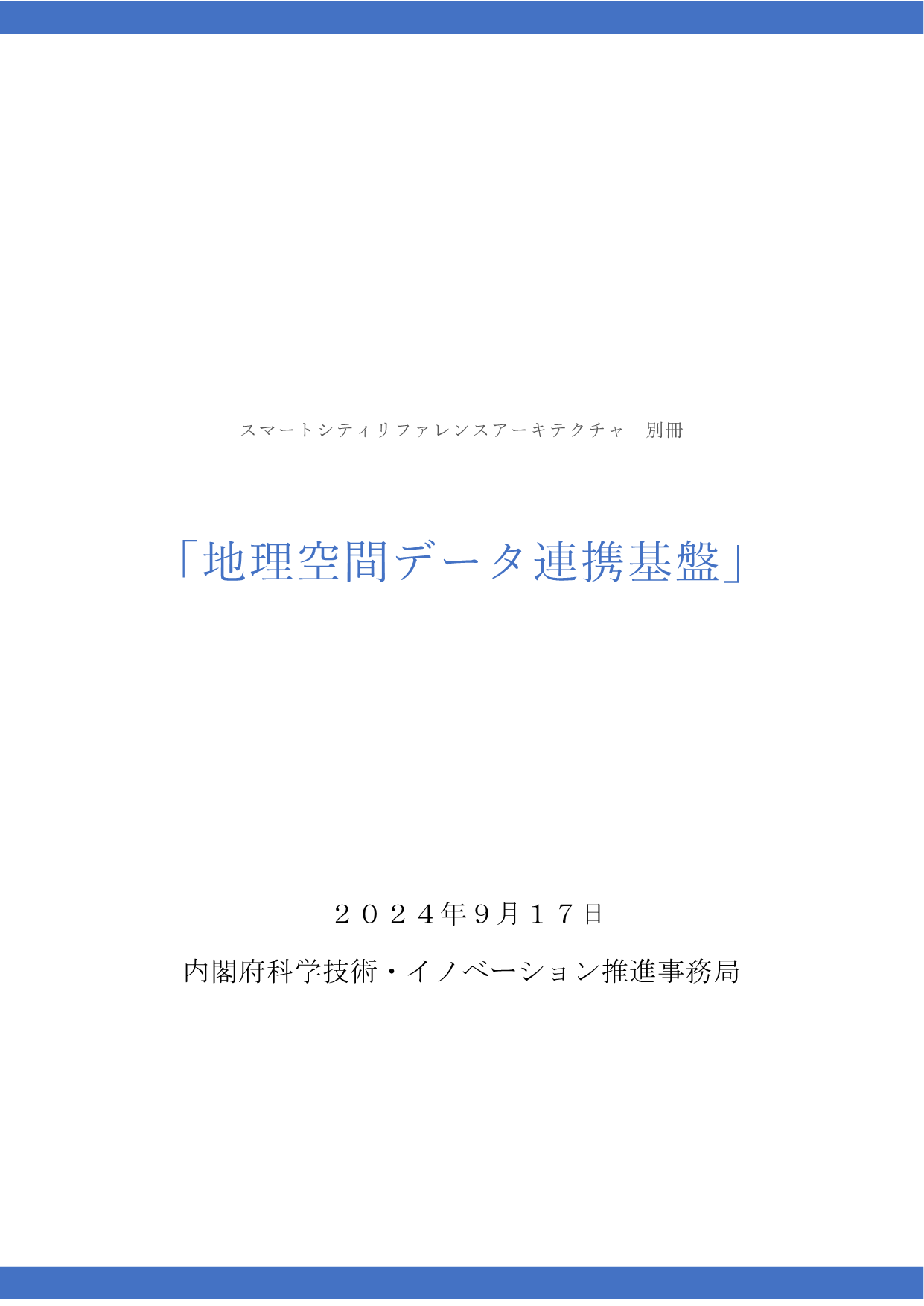
スマートシティ~地理空間情報データ連携基盤
先行してスマートシティに取り組む地域の事例について、関係者からのヒアリングを行った上でまとめた文書で、スマートシティの導入効果や進め方なども解説しています。取り組み事例は「初動段階」「準備段階」「計画(戦略)策定段階」「実証・実装~定着・発展段階」と、段階ごとにまとめられており、たとえば「実証・実装~定着・発展段階」の取り組み事例としては、「さりげないセンシングと日常人間ドック(荒尾市)」「ドローン買い物サービスの段階的なエリア拡大(伊那市)」の2つを紹介しています。
各地で進められているさまざまなスマートシティ関連施策に対して適切な評価の枠組み・評価指標を示し、適切な評価に基づいた施策改善を促進すことを目的とした文書で、ロジックモデルの作り方やポイントを解説するとともに、評価指標・KPIの適切な設定方法やポイントを紹介しています。