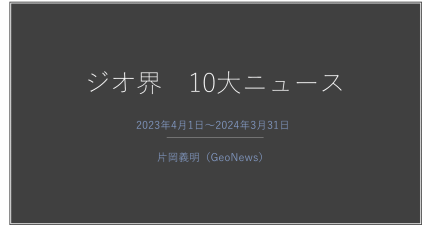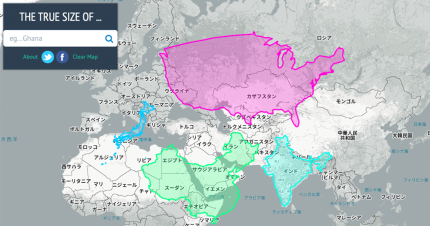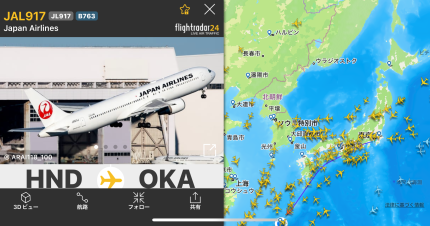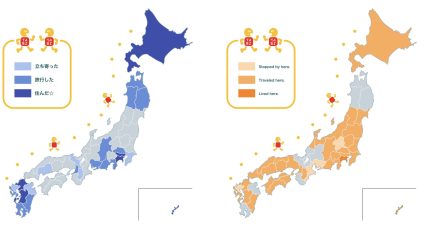内閣府とGeolonia、「地理空間データ連携基盤に関する勉強会」を開催
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局と株式会社Geoloniaは6月30日、「地理空間データ連携基盤に関する勉強会」を中央合同庁舎4号館(東京都千代田区)およびオンラインのハイブリッドで開催しました。
この勉強会は、地方自治体における地理空間データを活用した地域課題の解決に資することを目的として、地方自治体の職員などを対象に地理空間データの活用の基本的考え方やアーキテクチャと実装手順を具体的に学ぶための勉強会で、当日は地方自治体職員や地理空間データ連携基盤に関心のある国の機関の職員、民間企業の担当者など、現地とオンラインあわせて200名以上が参加しました。

開会挨拶
▽ 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 林誠氏
内閣府の林氏が開会挨拶として、内閣府がスマートシティの取り組みの一環として公表している「スマートシティリファレンスアーキテクチャ別冊『地理空間データ連携基盤』Ver.2」(2025年5月23日)について紹介しました。自治体では都市計画や交通、インフラ、防災など多様な分野で地図を利用する機会が多く、地図に多様な情報を重ねて行政の実務に活用したり、ウェブサイトやアプリケーションを通じて市民に情報を提供したりと、さまざまな用途に活用しています。ウェブサイトやアプリケーションを開発する場合、自治体が民間企業に発注することが多いですが、その際にオープンデータを活用することを同別冊では明確化するとともに、地図に関するさまざま情報を統一的かつ柔軟な方法で運用することについて規定しています。
これによりデータ連携を円滑に行いながらベンダーロックインを排除し、大手のベンダーだけでなく地域の企業も自治体からアプリケーション構築やメンテナンスを受託できる環境を作ることで、自治体の費用負担の低減や持続可能な自治体経営につながります。林氏は「この別冊『地理空間データ連携基盤』の趣旨に沿った取り組みが全国で広まっていくことを期待します」と語り挨拶を終えました。

基調講演「スマートシティ政策における地理空間データ連携基盤の位置づけ」
▽ 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 鈴木宏実氏
内閣府の鈴木氏が、政府のスマートシティへの取り組みにおける地理空間データ連携基盤の位置付けについて説明しました。鈴木氏は2025年5月23日に公表した「スマートシティリファレンスアーキテクチャ第4版(SCRA4.0)」について説明しました。同文書は財務省の予算執行調査で受けた指摘に基づいて、以下の4点に沿ってビジョンを示しています。
- 地域ごとの課題フォーカスでエコなシステムを目指す
- 地域ごとの住民の課題を収集できる枠組みの整備
- 分野間や都市間に取り残された人の課題解決が目的
- 分野間や都市間の課題を見つける仕組みが必要
このようなビジョンを実現するため、SCRA4.0では地理空間データ連携基盤を都市OSの中核に位置付けることを方針としており、デジタル公共財としての標準デジタル地図を定義し、その上にさまざまなデータを統合してオープン化していくことを目指しています。さらに、地域の課題やインフラ、不動産、山林・農地、交通事故、自然災害、地域交通などに関連した各種データについて、静的データだけでなく動的データも整備し、エコでオープンなデジタル地図とのデータ連携について検討する必要があります。データ連携によって多種多様なデータを標準デジタル地図に重ね合わせることで課題発見だけでなく課題管理にも活用し、地域の民間サービスにも利用可能にすることで、地域活性につながることが期待されています。
このように、日本におけるスマートシティの取り組みは、まず地理空間データ連携基盤の導入と市民参加から始めて、ベンダー主導の購買能力の高い人向けのウェルビーイングよりも、自治体主導の地域住民の公平・インクルーシブなウェルビーイングを優先して進めていく方針です。
SCRA4.0におけるスマートシティの進め方としては、まず地理空間データ連携基盤によって地図上に住民の課題を登録し、その中から優先すべき課題を検討します。そして住民とともに対策を検討し、施策を実施したあとは課題の把握に使用したデータを継続取得してKPI(重要業績評価指標)管理を自動化するという流れになります。
Society5.0では人間中心社会を目指すべきであり、例えば視覚障がい者にとって地図アプリが使いづらいものであるのならLLM(大規模言語モデル)やスマートグラスを活用して使いやすくするなど、将来的なシステムに変えていく必要があります。鈴木氏は「真の革新的な技術はインクルージョンから生まれます。インクルージョンの利用形態を考えて、発明・発見の原理原則を用いると、一般ユーザーにも便利なサービス開発ができるので、ぜひ皆様もインクルージョンから発案していただいて、スマートシティを盛り上げていただければと思います」と締めくくりました。

技術解説「基盤アーキテクチャ3層モデルと実装ポイント」
▽ 株式会社Geolonia 代表取締役 宮内隆行
Geoloniaの宮内が登壇し、地理空間データ連携基盤の概要と、基盤アーキテクチャの3層モデルと具体的な実装ポイント、そしてウェルビーイング向上やマイナンバーカードとの連携などについて解説しました。
地理空間データ連携基盤とは、さまざまなデータを地図に集約するプラットフォームであり、スマートシティの基盤となる“都市OS”をPCに例えた場合における「デスクトップ」に該当する仕組みと言えます。地理空間データ連携基盤をデスクトップとして活用することにより、空間を立方体で区切って付与する地理的ID「空間ID」を使ってデータを統合し、地図を使って色々なデータを可視化するとともに、APIやSDKを駆使して連携アプリケーションを作成することが可能となります。
地理空間データ連携基盤は、大きく分けて「データ層」「連携層(地理空間データ連携基盤インフラ)」「アプリケーション層」の3層に分けられます。データ層は特定のインフラを指すものではなく、CKANなど既存のオープンデータカタログやGitHub、Googleスプレッドシートなどインターネット上で利用できるさまざまなサービスを想定しています。連携層はこれらのデータにAPIでアクセスし、アプリケーション側で使いやすいフォーマットに変換して配信するためのインフラシステムで、このときに多様なセンサーデータや人流データなども統合してアプリケーションに提供することができます。アプリケーション層は公開型GIS(地理情報システム)や防災、観光、MaaSなどの各種アプリケーションを想定しています。
データ層については、まず自治体職員自身が便利だと思うデータから始めることが大事で、できるだけお金をかけないことでアップデートの回転数を上げることが重要です。また、所有権を渡す(配布する)のではなく、APIとして利用してもらうことを優先するほうが意思決定のハードルが下がります。データのフォーマットはそれほど重要ではなく、自動変換にしたほうが手間が減るしデータの品質向上にも有効です。
連携層については、インフラの仕組みは地図システム用のタイルサーバーの使用を推奨しており、オープンソースの地図ライブラリおよび空間ID用の共通ライブラリとともに、データ層のデータをベクトルタイル(PBF)またはデータPNGで配信することにより、それぞれのデータが別々の組織下のサーバーに保存されていてもデータ連携が可能となります。例えば防災システムの場合、A社の気象データ(データPNGタイル)、B社の人流データ(ベクトルタイル)、自治体のセンサーデータ、国土地理院の地形データ(データPNGタイル)を空間IDを軸にリクエストして組み合わせることで構築できます。
アプリケーション層については、例えば高松市の「高松マイセーフティマップ」の場合、従来のハザードマップのように災害リスクを色分けで表示するのではなく、自分の家や会社などの地点を指定すると、その地点の災害リスクを数値としてAPI経由で取り出して表示することができます。これによって細かいデータを捨てることなく複数の災害リスクをまとめて表示することが可能となります。このようなシステムを大規模なデータベースを構築することなく実現できるため、新たなサービスに挑戦しやすくなるし、自治体の垣根を越えてシステムを共用することも可能になります。また、ベンダーやデータホルダー、アプリケーションの開発会社のすべてについて別々の企業に依頼することができます。
このような地理空間データ連携基盤を構築することで、人流データと地理空間情報、ウェルビーイングに関するアンケートを組み合わせて幸福度と行動量、各種社会インフラとの関係を調査したり、マイナンバーカードを使った本人確認により居住地や個人属性に応じた、パーソナライズされた地理空間情報サービスを提供したりすることが可能となります。

講演「地理空間情報とデジタルIDの活用による主観・客観データを組み合わせた街づくり」
▽ xID株式会社 Co-Founder/代表取締役CEO 日下光氏
xIDの日下氏が登壇し、地理空間情報とデジタルIDを組み合わせたまちづくりの取り組みについて講演を行いました。デジタル化により行政サービスの利便性が向上する一方で、住民と行政の直接的な接点が減少し、新たなつながりの構築が課題となっており、住民ニーズの把握やデジタルデバイドによる情報格差の拡大、住民参画機会の減少による政策形成への影響などに対応するため、住民との接点を新たに構築する必要性が高まっています。さらに、従来の都市開発では経済的繁栄や利便性が重視されてきましたが、これからの街づくりでは住民の幸福度(ウェルビーイング)の向上が不可欠です。
人流データや施設利用状況などの地理空間情報と、住民アンケートや市民参加型合意形成プラットフォームなどデジタルID(マイナンバーカード)を活用した情報についても活用が広がっていますが、人流データについては、それが地域住民のデータであるかどうかの相関がわかりづらいという課題があります。一方、マイナンバーカードなどデジタルIDによる身元確認や当人認証については、部分最適・個別最適のデジタル化は進んでいるものの、各施策が住民のウェルビーイングや満足度の向上につながっているかどうかわからないという課題があります。このように、客観データ(地理空間情報)は集まりやすいが主観データ(デジタルID)との整合を取るのが難しく、主観データは取りやすいが客観データと併せた活用にまで至っていないという現状において、両者を組み合わせることで新たな価値を創出できる可能性があります。
地理空間情報とデジタルIDの統合アプローチにより、住民ニーズと行動の不一致の解消やデータに基づく政策形成の高度化、住民参加型政策形成の効率的実現、地域特性に応じた政策立案などが可能となり、人流データと意見・評価の紐付けによる精緻な分析や、住民幸福度と人流データ分析による相関関係の発見、政策効果の多角的検証と継続的改善などを実現できる可能性があります。このような統合アプローチの実現に向けた検討ポイントとしては、官民連携によるデータ共有基盤の整備やプライバシーに配慮したデータ活用ルールの確立、API連携による既存システムの有効活用などが挙げられます。
客観データと主観データの統合データの活用事例としては、高齢者の移動支援最適化や公園整備と健康増進効果、商店街活性化の効果測定、交通計画の最適化、公共施設や保育施設等の配置見直し、防災・安全対策などが挙げられます。両データを組み合わせることで、単独では見えなかった地域課題や住民ニーズが浮かび上がり、より精度の高い政策効果の評価が可能になります。
データ統合の実現に向けたステップについては、地理空間データ連携基盤の整備が進み、デジタルIDも普及が進んでおり、すでに土台はできあがっていると考えられます。今後は特定の地域や事業で小規模実証を行うことで効果検証と課題抽出を行った上で、データ統合・活用の法的枠組みを整備し、プライバシー保護と利便性のバランスを確保する必要があり、次のステップとして全地域への段階的展開と持続的な改善を行っていく必要があります。

事例紹介/パネルディスカッション
高松市、焼津市、那須塩原市の3市の担当者がパネリストとなり、Geoloniaの西川伸一(取締役COO)による司会で各市の事例紹介とパネルディスカッションが行われました。

事例紹介
高松市の地理空間データ基盤~分野・セクターを超えた共創モデル構築~
▽ 高松市 都市整備局都市計画課 デジタル社会基盤整備室 今田敦氏
高松市では、組織が持つ資源や課題をシェアリングすることで効率的な自治体運営の実現を目指しており、デジタル化によるシェアリングを実現するために地図が有効であると考えました。そこで、高松市が保有するデータや国・県が保有するデータ、民間が保有するデータなど多様なデータをWebAPIを介してつなげて、組み合わせることでさまざまなアプリやサービスを創出することを目指しています。同市では2022年度にデジタル田園都市構想推進交付金(デジ田)の採択を受けて地理空間データ連携基盤を構築し、防災や交通などさまざまなアプリケーションを作成できる環境を整備しました。地理空間データ連携基盤を構築したことにより、土台(ベース・レジストリ)の部分が効率的に運用できるようになり、その結果として庁内におけるBPRやサービス提供が可能となりました。同市はこれにより官民連携による持続可能なまちづくりを進めています。

スマートシティYAIZU 地図情報サービス実装の背景
▽ 焼津市 行政経営部DX推進課 スマートシティ推進室 早川隆之氏
焼津市はDX推進計画を2021年に策定し、その中のリーディングプロジェクトの1つとしてスマートシティの推進を掲げています。2022年度にはデジ田でデータ連携基盤を活用した地図サービス等の実装にチャレンジし、同基盤をもとに「焼津データマップ」を構築しましたが、UIの動きが重く、コストがかかり、地図の共有(パーマリンク)ができないといった課題が発生しました。そこで2023年度に市民や職員から意見を聴取し、焼津データマップの改善策を検討した上で、2024年度、2度目のデジ田で地理空間データ連携基盤を活用した「スマートマップ焼津」を実装しました。スマートマップ焼津は焼津データマップの課題を改善し、高速・快適な表示が可能で、GitHubの利用により機動的な公開が可能となりました。さらに、共有・2次利用も容易で、データを一元的に表示できるようになりました。同市ではこのスマートマップ焼津を利用してリアルタイム防災マップなどを提供しています。今後は市民参加の促進や庁内横断的なGISの運用、行政サービス以外でのサービス創出などに取り組んでいく方針です。

那須塩原市×地理空間データ連携基盤
▽ 那須塩原市企画部デジタル推進課デジタル政策係 髙久健氏
那須塩原市ではDX推進戦略を策定し、そこで示された基本方針の取り組みをアクションプランとして具体化しています。これをもとに、2022年度にBPR(業務改革)の一環で全庁的な課題抽出アンケート調査を実施し、2023年度にアンケート結果を踏まえた全庁的な課題抽出とヒアリングを実施しました。この結果、さまざまな部署の課題がGISにより解決につながることが見えてきました。現在、「お役立ち!まち情報プラットフォーム構築事業」として、統合型GISおよび公開型GIS、地理空間データ連携基盤を構築中で、2026年3月から運用開始を予定しています。

パネルディスカッション
スマートシティやDXの取り組みと地図との関係について
今田氏「自治体の事務の多くは位置情報に関連しており、地図と役所の事務は非常に相性が良いです。地理空間データ連携基盤を使ってオープンデータを可視化することで市民が窓口に来なくても家で見られるようになり、役所を訪れる人が減ることで職員の負担も減らすことができます。高松市のアプリケーションのように、課題を整理してサービスにすることも可能になるので、地図は活用性が高いと思います」
地理空間データを扱う場合の課題について
早川氏「焼津データマップでは、津波や洪水の浸水想定区域などの大きなデータ(ポリゴン)を表示する際に、時間がかかったり他のデータと重ねて表示できなかったりする場合があり、新規データを追加するのに多大なコストがかかり、データの登録や更新に時間がかかることも課題となっていたため、そのような課題を解決するソリューションを探すことにしました。現在のスマートマップ焼津では、運用体制の構築に取り組んでおり、理想は庁内の共有GISでデータを生成し、公開できるものはそのままGitHubに送り、承認が通れば公開GISで公開されるという流れを目指しています」
データの公開・非公開について
髙久氏「統合型GISで管理している情報のうち一部を公開型GISで公開する方針で、担当課と話し合いながらどのデータを公開するかを決めていきたいと思います」
今田氏「防犯上のリスクがある場合はデータの公開をよく検討する必要がありますが、担当課が『公開しないほうがいい』という根拠がしっかりしていない場合は、『なぜ公開してはいけないデータなのか』『なぜそのように考えるのか』といった疑問に対して担当課以上に詳しくならないと説明ができません。公開する場合は担当課の話をしっかりと聞いて公開することがBPRにつながり、制度上においても公開する必要性が高いことを納得していただく必要があります」
早川氏「やはりデータを公開することで職員の仕事が楽になるということはきちんと伝える必要があるし、それが市民のためにもなることを伝えることで納得してもらいやすくなると思います」
アプリケーションの作成について
今田氏「例えば水防アプリでは、台風の警報が発令されたときに発災情報を管理し、警報の内容を登録することが可能で、通行止めの情報を地図上に表示することもできます。このシステムを活用して道路使用の承認の機能を追加することで、道路使用の許可申請機能を加えることが可能となります。これによりBPRが進み、承認されたデータは色々な用途に活用できます。交通系のアプリケーションについては、もともとは駐車場を探してうろつく車が多いために発生する渋滞を解消する仕組みとして構築したのですが、これ以外にも高松市はGTFSを活用したアプリケーションやサービスが充実しています。地域で持っているデータと施設情報やイベント情報を連携し、地図をハブにしてデータを集約することで、公共交通において新しい形ができると考えています」
国・県・市区町村の共同利用の考え方について
早川氏「例えば静岡県内の自治体の多くは県のデータを利用していますが、GitHubなどでいつでもデータを公開できる仕組みを関係者で共有することができれば、最新のデータをすばやく利用できるようになると思います。できればもっと広域で共同利用の基盤が整備され、そこに皆さんがデータを入れ合うような仕組みのほうが良いと思います」

講演「市民・都市・自然空間のウェルビーイング創造の新手法を考える」
▽ 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート 代表理事 南雲岳彦氏
スマートシティ・インスティテュートの南雲氏が登壇し、ウェルビーイング創造の新たな手法について解説しました。2025年の「世界幸福度報告(WHR)」によると、日本の幸福度は55位であり、日本は「1人当たりGDP」や「社会的支援」「健康寿命」の評価が高い一方で、「人生の選択の自由度」や「寛容さ・気前の良さ」「政府への信頼」についての評価が低く、日本の閉塞感はこのような点に起因していると考えられます。
市民の「暮らしやすさ」と「幸福感(Well-being)」を数値化・可視化する指標である「地域幸福度(Well-Being)指標」を見ると、日本全体では都市機能や自然への評価が高い一方で、遊び・娯楽や多様性・寛容性、事業創造に関する評価が低めとなっています。総合指標(幸福度、生活満足度等)に相関性の高い主観因子のランキングを見ると、「公共空間」「教育機会の豊かさ」「事故・犯罪」「地域行政」など7因子が共通項となっており、今年のランキングでは「地域の人間関係」がトップ圏外となりました。また、収入については、年収2,000万円以上で幸福度が頭打ちとなる“イースタリンパラドックス”が観測されました。さらに、生活評価(人生評価)の設問を使ってGDW(国内総充実度)を掲載した際、最もGDWが高いのは東京都となりました。
このほか、自由記述について形態素解析を実施し、単語ごとの頻度を抽出してワードクラウドを作成したところ、「自分のまちの好きな点」のワードクラウドでは「自然」、「自分のまちの改善すべき点」では「交通」を挙げる声が多かったことがわかりました。
現在の取り組みとしては、従来のウェルビーイングの指標は1人1人にアンケートを行って平均値を算出していたのに対して、地方創生や脱炭素などの大きな課題と一体化させるために、新たな算出方法に取り組んでいます。新たな算出方法としては、主観的幸福度や健康寿命、地域人口などから算出される「地域総幸福量」と、衛星データや航空写真などの地理空間情報をもとに可住地面積を組み合わせてまちが変わっていく状況をダイナミックに反映して算出する「地域における総幸福量の空間効率」や、地域総幸福量とCO2排出量を組み合わせた「地域における総幸福量の環境効率」などがあります。
ウェルビーイング関連のデータについては現状、関連データが分断されているため、今後は統合的な基盤の整備が必要であり、関連データの集積や分析・評価、AI、ビジネスモデルなどのコモンズ化を目指す必要があります。市民のウェルビーイング向上を進めるためには主観と客観を組み合わせたアプローチが重要であり、とくに日本の弱みである「文化・意味づけ」の要素を強化していくことが重要となります。

「スマートシティ実現のための地理空間データ連携基盤スマートマップ」
スマートシティの基本から事例が書かれた資料がダウンロード可能です。