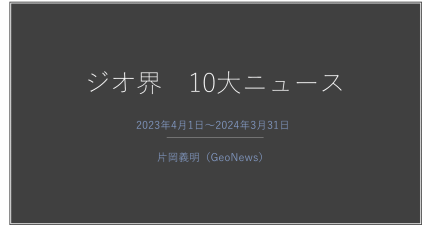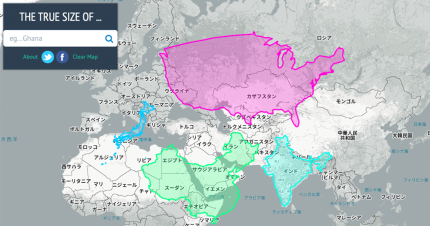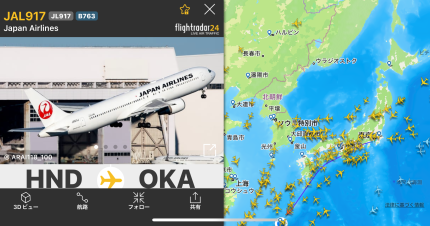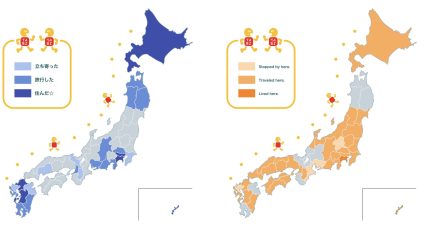オープンな技術を活用して社会課題を解決、多彩な分野に長けた地理空間情報の専門家チームがGeoloniaに参画
Geoloniaは2025年6月、合同会社Georepublic Japanの事業を譲受することで合意しました。Georepublic Japanはオープンソースソフトウェアやオープンデータを活用したGISソリューションを提供してきた企業で、同社の代表を務め、今回の事業譲渡によりGeoloniaに参画した関治之は、国のデジタル化推進、位置情報ビジネス、オープンソースコミュニティにおける第一人者として知られており、シビックテックコミュニティの支援組織である一般社団法人コード・フォー・ジャパンの代表理事や共創イベントの企画・運営に取り組む株式会社HackCampの代表取締役会長、東京都チーフデジタルサービスフェロー、神戸市チーフ・イノベーション・オフィサー、総務省地域情報化アドバイザー幹事、デジタル庁シニアエキスパートなどの要職を務めています。
Georepublic Japanのこれまでの歩みと今回の事業譲渡を決めた理由、そして今後の展望について関に話を聞きました。

――Georepublic Japanの設立経緯について教えてください。
関 Georepublic Japanは2009年に、地理空間情報を活用してさまざまな社会の課題を解決したいという思いで立ち上げました。とくにオープンソースソフトウェアやオープンデータなど、オープンな技術を使って社会課題を解決する活動を展開し、地理空間データやIoT、オープンガバメントとシビックテック、地図デザイン、ルート最適化、3D点群データと拡張現実、ビッグデータ、空間分析、ネットワーク分析など多彩な分野に長けた専門家チームとしてこれまで成長してきました。
――設立当時はどのような活動をしていたのでしょうか?
関 最初はIPA(情報処理推進機構)の未踏IT人材発掘・育成事業に、我々が開発を提案したオープンソースの経路探索の仕組みが採択されたので、その開発に取り組みました。この経路検索の仕組みを使ってオンデマンドのバスの配送サービスを作成したプロジェクトは、オープンソースソフトウェアの社会実装の一例としてGeorepublic Japanのターニングポイントとなりました。このほかには、航空測量会社など色々なデータを保有する企業から「情報をわかりやすく見せたい」という要望をいただき、ウェブサイトやモバイルアプリなどを使って3Dデータを含めた大量の地理空間データを可視化するといった仕事もありました。基本的なスタイルは受託開発で、お客様の要望に合わせてシステムをスクラッチで開発することが多かったです。
初期の頃は幅広い分野の仕事を手がけましたが、徐々にGIS(地理情報システム)に特化した仕事が多くなっていきました。とくにモバイル端末を使った現場での作業記録や、ルート検索システムの構築、OpenStreetMap(OSM)の地図データの分析など、地理空間情報に関する専門的な仕事が多く、BtoBtoCよりもBtoBtoBのような“裏方”の仕事が多かったです。
――「My City Report」などシビックテック関連の案件や、官公庁や自治体に関連した仕事も手がけられていますね。
関 「My City Report」は東京大学との共同研究により、千葉市の市民協働サービス「ちばレポ」をベースにオープンソースによる市民協働プラットフォームとして開発し、現在は全国の自治体に広がっています。(現在は、株式会社アーバンエックステクノロジーズに事業譲渡)。自治体関連の仕事としては、例えば東京都の道路局が管理する監視カメラや水位センサーなどのデータをオープンソースのプラットフォーム「FIWARE」を使って収集し、ひとつのダッシュボードで見られるツールを作りました。これによって台風や大雨のときにどこでどのようなことが起きているかを一元的に見ることができます。

――Georepublic Japanが他の企業とは違う特徴的な点を教えてください。
関 もともとは私とダニエル・カストゥル、アントン・パトルシェブの3人で始めた会社で、英語を社内公用語にして、できるだけ海外の案件を取りに行こうとしていたのは特徴的だったと思います。例えば海外の政府の助成金などを利用して経路探索のプログラムを開発するなど、コロナ禍以前は海外の案件を数多く手がけていました。
また、海外のFOSS4G(地理空間情報に関するオープンソースソフトウェアのコミュニティ)関連のイベントにも積極的に参加し、そのようなイベントで培ったネットワークを駆使しながら、最先端の地理空間技術をうまく採り入れて活動していたのもユニークだったと思います。例えばオープンソースのツールを使う上で、我々だけでは対応できないようなコアの部分の修正が必要な場合は、そのプロジェクトに携わっている人に問い合わせて直接やりとりするといったことも行っていました。
――会社の方針が大きく変わったことなどはありましたか?
関 設立当初は3人から始まり、今年の事業譲渡の時点では20人までスタッフが増えましたが、ビジネスのスタイルが受託開発で、オープンな技術を活用するという基本的な方針は一貫しています。そしてオープンソースソフトウェアを使わせていただく以上、「コントリビューションという形でOSSコミュニティに貢献する」という考えにも変更はありません。
――今回、Geoloniaへの事業譲渡を決めた理由をお聞かせください。
関 最も理由として大きかったのは、スタッフにもっと活躍できる場を与えられると思ったことです。これまで15年の間、受託開発を続けてきたわけですが、受託開発は毎回ゼロの状態から作り上げていくため、ノウハウが溜まるし、仕事としてもやりがいがあって面白い案件も少なくありません。しかし、その反面、毎回スクラッチで開発するのはビジネスとして大きく広がりづらいという課題もありました。
我々はGISのスペシャリストとして色々なことができる力がある一方で、プロダクトとして仕上げる力や、お客様側への提案力という面ではGeoloniaのほうが優れているなと思っていた部分があるので、事業譲渡によりお互いの良さを補えると思いました。
Geoloniaは現在、自治体や企業が持つ様々なデータを集約してアプリケーション開発を容易にする「地理空間データ連携基盤」を提供しており、Georepublic Japanは地理空間データの扱い方や、バックエンドの処理の仕方などについて知見を持っているので、両社はとても相性が良い組み合わせだと思います。事業譲渡する前にも両社で一緒に仕事をしたことがあり、相性が悪くないことが事前に確認できたことも大きかったです。
――Geoloniaについては、もともとどのような印象を持っていましたか?
関 従来のGISの文化とは異なる、新しいやり方で地理空間情報のソリューションを提案する会社という印象を持っていました。ユーザーインターフェイスにこだわり、お客様の目線でわかりやすく便利なサービスを提供している点や、オウンドメディアによる情報発信、さまざまな関係者への働きかけを積極的に行っている点にも良さを感じていました。また、代表の宮内さんはオープンソースのコミッターだったという経験もあり、オープンソースに関する技術的なところもわかっていて「センスがあるな」という印象でした。
――今回の事業譲渡で2社の融合したことにより、今後どのようなシナジーが生まれることを期待しますか?
関 Geolonia Mapsなどのプロダクトを育てつつ、より特化した形で我々のノウハウを注ぎ込みながらお客様の課題を解決するということができれば嬉しいし、とてもワクワクします。GISのシステムにおいて「どのようにデータをハンドリングするべきか」「サーバーをどのように構築するべきか」といった点については、我々がこれまで培ってきた知識はかなり役に立てると思います。
また、今後AIによる開発が普及し、より上流工程においてどのように創造性を発揮していくかが大事になっていく中で、ジオテクノロジーズのグループ会社ということで地図データや人流データを活用してソリューションを提案できるのは大きいと思っています。Georepublic Japanでは、技術はあってもデータが無いから価値を提供しきれないということがあったので、グループが保有するデータを活かして、「このデータを分析するともっと価値が出る」ということを具体的に提案できるのは良いなと思います。
――近年のジオ業界の動向と、今後の展望についてお聞かせください。
関 Geoloniaのようなオープンソースソフトウェアやオープンデータを活用する企業が色々なクライアントと一緒にサービスを作り上げていくという流れが中心となりつつあり、今後はデータの相互運用やAPIによる連携などにより、一社だけですべてを囲い込むのではなく、多様なプレーヤーで課題を解決していくという価値観が共有される動きがより進むと思います。
これまでもGISの業界は、データ形式を独自形式ではなく国際標準に合わせていこうという動きが他の業界に比べて進んでいましたが、今後はそのような考え方がスマートシティや街づくり、インフラ整備など、現実社会の課題解決においてより重要視されていくと思うし、社会全体の中においても、そのような動きを牽引するような業界になると思っています。
昔はGISといえば土木など特定分野だけで使われるものでしたが、今では街づくりや観光、教育、福祉など、他の分野でも当たり前に利用されているので、GIS業界という狭い範囲で考えるのではなく、色々な情報がつながるプラットフォームを拡大していくという意識が大事だと思います。そのためにも、ただ単に“GISのマップを提供します”ということではなくて、その上に色々なサービスを展開できる社会的な基盤を提供していく活動をGeoloniaでも続けていきたいと思います。